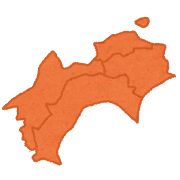
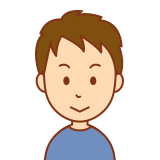
四国の武将って長宗我部しか知らない
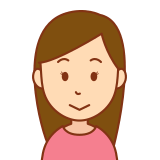
四国の歴史を知りたい
*この記事はそんな方に向けて投稿しました
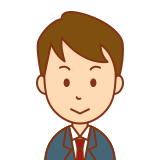
こんにちは!
歴史オタクのりょーすけです!
今回は四国の武将についてまとめました!
紹介するのは以下の武将です!
・長宗我部元親
・三好長慶
・河野道直
難しい用語は使わず、かみ砕いて説明したので、楽しく読んでらえたら嬉しいです
長宗我部元親
長宗我部元親(ちょうそかべもとちか。1539–1599)は、戦国時代の土佐国(現在の高知県)の戦国大名で、長宗我部氏第21代当主です。
初陣(長浜の戦い)は22歳と遅かったが、勇猛果敢な戦いぶりで「鬼若子」と称されました。
一領具足を活用し土佐を統一、さらに阿波・讃岐・伊予へ進出し四国をほぼ制圧。
しかし1585年、豊臣秀吉の四国征伐により降伏し、土佐一国の領有に留まりました。
晩年は「長宗我部元親百箇条」を制定し、領国統治に尽力しました
初陣(長浜の戦い)
「長浜の戦い」は、1560年に土佐国(現在の高知県)で起きた戦国時代の戦いで、長宗我部元親の初陣として知られています。
この戦いは、長宗我部氏と本山氏との間で行われ、元親の軍事的才能が初めて発揮された重要な戦いです。
当時、長宗我部家は土佐の覇権を巡って本山氏と対立していました。
父・長宗我部国親は、敵方の長浜城を攻略するため、内部からの調略を計画します。
1.調略成功
国親は、かつての家臣・福留右馬丞(ふくとめうまのじょう)を通じて長浜城の門を内部から開かせ、無血開城に成功。翌日には本山軍との本戦「戸ノ本の戦い」が勃発。
2.元親の初陣
22歳の元親は50騎を率いて出陣。
敵陣を突破し、70余の首を挙げるなど大活躍。
3.潮江城の奪取
勝利の勢いで本山方の支城・潮江城も制圧。
この戦いをきっかけに、元親は「姫若子(ひめわこ)」と呼ばれていた軟弱な印象から一転、「鬼若子(おにわこ)」と称されるようになり、土佐統一への道を歩み始めます。
一領具足
「一領具足(いちりょうぐそく)」とは、長宗我部元親が土佐統一の過程で整備した独自の兵制で、農民が普段は農業に従事しながら、戦時には武装して兵士として出陣する制度です。
「一領」とは一式の武具(鎧・兜・槍など)を意味し、「具足」は武装のこと。
農民が自前の武具を持ち、必要に応じて召集される。
常備軍ではなく、臨時に動員される民兵的存在。
元親はこの制度により、短期間で大量の兵力を動員可能にし、四国制覇の原動力としました。
コスト削減:常備軍を維持する費用が不要。
即応性:農民が武装してすぐに戦場へ向かえる。
忠誠心の強化:領主との直接的な関係が強く、士気が高い。
長宗我部元親百箇条
「長宗我部元親百箇条」は、戦国大名・長宗我部元親とその子・盛親が1597年に制定した分国法で、土佐国(現在の高知県)を統治するための基本法典です。
全100条から成り、政治・軍事・刑罰・農政・宗教など多岐にわたる規定が盛り込まれています。
特徴的なのは、喧嘩や密通などに対する厳罰主義で、違反者は理非を問わず処刑される条文もあります。
また、鉄砲や弓馬の習得を奨励し、武士の武芸向上を図る一方、農民の隠田を厳しく取り締まるなど、領内の秩序維持と生産力の安定を重視していました。
豊臣政権を「公儀」として尊重する姿勢も見られ、中央政権との協調を意識した内容となっています。
戦歴
土佐統一までの戦い
1560年:長浜の戦い
初陣で本山氏と戦い勝利。これを機に家督を継ぎ、長宗我部家の当主となる。
1568年:本山城の攻略
本山氏を降伏させ、土佐中部を制圧。
1569年:八流の戦い
安芸国虎を破り、土佐東部を平定。
1575年:四万十川の戦い
一条兼定を破り、土佐一国を統一。
四国制覇への拡大戦
1576年~1584年:阿波・讃岐・伊予への侵攻
阿波の三好氏、讃岐の香川氏、伊予の土豪らと戦い、四国の大部分を制圧。
1582年:中富川の戦い
三好氏(十河存保)を破り、阿波の支配を確実に。
1584年:四国統一達成
阿波・讃岐・伊予を手中に収め、四国の覇者となる。
豊臣政権下での戦い
1585年:豊臣秀吉の四国征伐
10万を超える大軍に抗しきれず降伏。土佐一国のみを安堵される。
1586年:戸次川の戦い
九州征伐に参加。島津軍に敗北し、長男・信親が戦死。
1590年:小田原征伐
水軍を率いて下田城を攻略、小田原城包囲にも参加。
1592年・1597年:文禄・慶長の役(朝鮮出兵)
豊臣秀吉の命で朝鮮に出兵。
三好長慶
三好長慶(みよしながよし。1522年~1564年)は、戦国時代の武将で、阿波国出身(現在の徳島県)の三好元長の嫡男です。
若くして父を失いながらも頭角を現し、主君・細川晴元を凌ぐ実力を持つようになります。
将軍・足利義晴・義輝を京都から追放し、幕府の実権を掌握。
畿内を中心に勢力を拡大し、「三好政権」を築きました。織田信長に先駆けて天下を掌握したとも評され、「戦国最初の天下人」とも呼ばれます。
晩年は家族の不幸が続き、43歳で病没しました。
三好政権
三好長慶の政権、通称「三好政権」は、1549年から1568年までの約20年間、畿内(京都周辺)を中心に展開された戦国時代の武家政権です。
これは、室町幕府の権威が衰退する中で、実力によって中央政権を掌握した初の事例とされ、織田信長に先駆けた「戦国最初の天下人」とも評されます
三好長慶は、父・三好元長の仇である細川晴元に反旗を翻し、1549年の江口の戦いで勝利。
将軍・足利義晴・義輝を近江に追放し、京都の支配権を掌握しました。
これにより、細川政権は崩壊し、三好政権が成立します
将軍・管領を傀儡化:
足利義輝や細川氏綱を形式上の権威として利用し、実権を掌握。
本拠地の移転:
摂津国芥川山城から河内国飯盛山城へ移し、政権の安定を図る。
広域支配:
阿波・讃岐・淡路・摂津・河内・和泉・山城・大和・丹波・若狭・播磨など13カ国以上を支配し、当時の戦国大名の中でも最大級の勢力を誇った
*現代でいうと以下の支配範囲
- 四国地方:徳島県、香川県
- 近畿地方:大阪府、京都府、奈良県、兵庫県
- 北陸地方:福井県(若狭)
- 中国地方の一部:兵庫県西部(播磨)
中央集権的な性格:
地方政権ではなく、京都を中心とした中央政権として機能。
儀礼的な幕府との関係:
形式的には室町幕府の秩序に従いつつ、実質的には独立した政権運営。
一族・家臣団の支援:
弟たちや松永久秀らの支援により、政権を維持。
軍事力の構成:
一族による分担統治と軍事指揮
三好実休(阿波方面)
安宅冬康(淡路方面)
十河一存(讃岐方面)
野口冬長(播磨方面)
これらの弟たちが各地の軍事を担当し、迅速な対応が可能でした
松永久秀・松永長頼の活躍:
久秀は政務・謀略に長け、長頼は合戦の名手として軍事面で活躍。
特に久秀は後に大和支配を巡って筒井順慶と争うなど、三好政権の軍事的中核を担いました
1560年代に入り、嫡男・義興や弟・実休、一存らが相次いで死去。
政権の中枢を担う人材が失われ、内部崩壊が進行。
1564年、長慶自身も病没し、三好政権は急速に弱体化。
後継の三好三人衆は足利義輝を殺害するなど混乱を招き、織田信長の台頭を許すことになります
三好三人衆(みよしさんにんしゅう)とは、戦国時代に畿内(現在の近畿地方)で勢力を持った三好氏の重臣たち、すなわち以下の三人を指します
- 三好長逸(みよし ながやす)
- 三好宗渭(みよし そうい)(実名は政勝または政生)
- 岩成友通(いわなり ともみち)
三好三人衆は、三好長慶の死(1564年)後に、若年の後継者・三好義継を補佐する形で三好政権を支えました。
三好長慶の弟たちもすでに亡くなっていたため、政権の実権はこの三人に集中しました。
彼らは軍事・政治の両面で活躍し、特に1565年には室町幕府13代将軍・足利義輝を暗殺する「永禄の変」を引き起こし、幕府の権威を大きく揺るがしました。
その後、三好義継や松永久秀との対立が激化し、三好政権は内紛状態に陥ります。
この混乱を利用して織田信長が上洛(1568年)し、三好三人衆は信長に抵抗するも敗北。
勢力は急速に衰退していきました。
戦歴
1542年:太平寺の戦い
細川晴元方として木沢長政を討ち取る。
1547年:舎利寺の戦い
細川氏綱・遊佐長教を破り、畿内支配を強化。
1549年:江口の戦い
一族の三好政長を討ち、細川晴元・足利義晴・義輝を近江へ追放。三好政権の始まり。
1551年:相国寺の戦い
細川晴元の京奪回を阻止。
1558年:北白川の戦い
四国勢を率いて従軍、畿内支配を維持。
1560年:河内の戦い
畠山高政・安見宗房を破り、河内守護に任命される。
1562年:久米田の戦い
弟・三好実休が畠山高政に敗れ討死。
1564年:飯盛山城で病死
政権は三好三人衆に引き継がれるが、急速に衰退。
江口の戦い
江口の戦い(えぐちのたたかい。1549年)は、三好長慶が同族の三好政長を討ち、畿内支配を確立する契機となった重要な戦いです。
三好長慶は細川晴元の家臣として頭角を現すが、父・元長の死に政長が関与していたとされ、長慶は政長を「父の仇」として敵視。
細川晴元が政長を庇護したため、長慶は晴元を見限り、細川氏綱派に転じて対立を明確化
政長は江口城に布陣。
江口は淀川と神崎川に囲まれた要害だが、退路を断たれると孤立する地形。
長慶は江口城を包囲し、食料の道を断ち、弟・安宅冬康と十河一存らを北側に派遣して退路を遮断。
6月12日から戦闘開始。政長は援軍の六角軍を待つが、長慶は6月24日、六角軍到着直前に総攻撃を仕掛ける。
政長は討死、または淀川で水死したとも。
地形の利用:川に囲まれた江口城の弱点を突いて包囲。
退路遮断:別府川沿いに布陣し、政長軍の連絡線を断絶。
迅速な決断:援軍到着前に決着をつけるための強襲。
久米田の戦い
久米田の戦い(くめだのたたかい)は、永禄5年(1562年)3月5日に現在の大阪府岸和田市で行われた合戦で、三好政権の中核を担っていた三好実休(みよしじっきゅう)が戦死したことで知られています。
この戦いは、三好長慶の政権にとって大きな転機となりました。
三好政権は畿内を支配していたが、弟・十河一存(そごうかずまさ)の死(1561年)により南方の守りが手薄に。
これを好機と見た畠山高政と南近江の大名六角義賢が連携し、三好政権に対して挙兵。
畠山軍は岸和田城を包囲し、三好実休は救援のため出陣。
三好実休は貝吹山(久米田寺周辺)に布陣。
畠山軍は魚鱗の陣で進軍し、春木川を渡って攻撃開始。
三好軍は前衛・篠原長房、右翼・三好康長、左翼・三好宗渭、中堅・三好盛政、本陣・実休という布陣。
一時は三好軍が優勢だったが、畠山軍の第三陣・湯川直光隊が背後を突く。
実休は本陣の兵を前線に投入しすぎて手薄となり、根来衆の鉄砲隊の奇襲を受けて討死。
三好実休の戦死により三好軍は総崩れ。
畠山高政は和泉・南河内を奪還。
三好政権は軍事的・精神的支柱を失い、以後の衰退のきっかけとなった
この戦いは、三好政権の「転落の始まり」とも言われ、戦国時代の政権交代劇の一幕として非常に重要です。
河野道直
河野通直(かわの みちなお、1564年または1566年生〜1587年没)は、伊予国(現在の愛媛県)の戦国大名・河野氏の最後の当主です。
毛利氏の支援を受けて政権を維持しましたが、豊臣秀吉の四国攻めにより降伏し、所領を没収されました。
晩年は広島県竹原で過ごし、23歳で病死または自害したとされます。
彼の死後、養子の河野通軌(かわのみちなり)が家名を継ぎましたが、大名としての再興は果たせませんでした。
当時の河野氏はすでに衰退しており、家臣の反乱や長宗我部氏の圧力に苦しんでいました。
通直は毛利輝元の姪・矢野局と結婚し、毛利家との結びつきを強化しますが、1585年の豊臣秀吉による四国攻めでは、湯築城に籠城するも小早川隆景に降伏。
所領を没収され、伊予の大名としての河野氏は滅亡しました
1.家督相続と内乱の鎮圧(1568年〜)
永禄11年(1568年):幼少で河野氏の家督を継ぐ。
家中では家臣・大野直之の反乱が発生。大野は長宗我部氏と通じていたが、通直は毛利氏の支援を受けてこれを鎮圧。
2.長宗我部元親との対峙(1570年代〜1580年代)
天正4年(1576年)以降:長宗我部元親が四国統一を目指して伊予に侵攻。
河野氏は一時的に長宗我部氏に降伏したとされるが、毛利氏の後ろ盾を得て独立を維持しようとする。
天正9年(1581年):毛利輝元の姪・矢野局と婚姻し、毛利との関係を強化。
3.豊臣秀吉の四国攻め(1585年)
天正13年(1585年):秀吉の命を受けた小早川隆景が伊予に侵攻。
通直は本拠・湯築城に籠城し、約1か月間抵抗。
最終的に降伏し、所領を没収される。これにより河野氏は戦国大名として滅亡。
4.降伏後と最期(1585年〜1587年)
降伏後は広島県竹原に移され、天正15年(1587年)に病死または自害。
一説には、秀吉と毛利輝元の意向により自害させられたとも言われています。
河野通直の戦歴は、地方大名が中央政権の圧力に屈していく過程を象徴しています。
彼の戦いは、軍事的勝利よりも、外交と家名存続のための政治的選択に重きを置いたものでした。
投稿者から一言
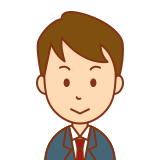
最後までご覧いただきありがとうございました
戦国時代の四国の歴史について少しでも理解して頂けましたか?
個人的には河野家の近隣の大名に翻弄された人生が、下剋上をリアルに物語っているように感じました
これからも分かる、面白いをモットーに投稿を続けていくのでぜひご覧ください!
前回は九州の武将(大友・龍造寺・島津)について解説しました!
ぜひご覧ください<(_ _)>

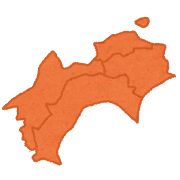


コメント