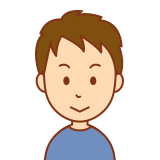
村上海賊の歴史を知りたい
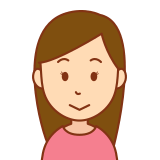
村上海賊と毛利家との関係は?
*この記事はそんな方に向けて投稿しました
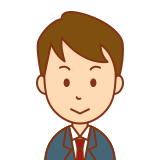
こんにちは!
歴史オタクのりょーすけです!
今回は村上海賊について解説しました
実は、村上水軍は海賊事業のあくまで一つの役割で、普段は商人の船の護送や水先案内をしていました
そんな村上海賊が戦国の世でどのような影響を与え、歴史に名を残したのか、ぜひご覧ください
村上海賊とは
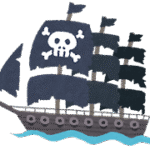
村上海賊は、室町時代から戦国時代にかけて瀬戸内海で活躍した海賊集団です。
因島(いんのしま)・能島(のしま)・来島(くるしま)の三家から成り、海上交通の安全を守る代わりに通行料を徴収する制度を築きました。
毛利氏などの大名に仕え、厳島の戦いや木津川口の戦いで活躍。
戦術・航海技術に優れ、戦国時代の海の支配者として重要な役割を果たしました。
村上海賊の生業(なりわり)
1.水先案内人
芸予(げいよ)諸島は瀬戸内海の中央に位置し、大阪や九州へ向かう海上交通の要所でした。
潮流(ちょうりゅう)が激しく、航行には熟練の技術が必要だったため、村上海賊は水先案内人としても重宝されました
2.通行料徴収:
海峡を関所に見立て、通行料を徴収することで海上支配を確立。
安全な航行を保障する代わりに料金を取るという、現代の通行税のような仕組みを持っていました
3.軍事活動と外交:
毛利氏や小早川氏などの大名に仕え、水軍として戦闘にも参加。
特に能島村上氏は第一次木津川口の戦い(1576年)で織田軍を撃破するなど活躍しました
4.交易と漁業:
平時には漁業や中国などとの交易も行い、海とともに生きる人々としての側面も持っていました
毛利家と村上海賊の関わり
1.毛利元就の台頭と水軍の必要性
毛利元就が中国地方で勢力を拡大する過程で、瀬戸内海の制海権を握ることが戦略的に不可欠となりました。
そこで、彼は安芸武田氏の旧臣や小早川氏の水軍を取り込み、毛利水軍を形成しました
2.小早川隆景と村上水軍の接点
毛利元就の三男・小早川隆景が小早川家を継ぎ、毛利家と小早川家が一体化すると、瀬戸内海の海賊衆である村上水軍(三島村上家:能島・因島・来島)との関係が深まりました
3.厳島の戦い(1555年)での協力
この戦いでは、毛利水軍と小早川水軍に加え、村上水軍が200〜300艘の船で援軍として参戦。
陶晴賢(すえはるたか)の軍を奇襲し、毛利方の勝利に大きく貢献しました
4.村上三家の対応の違い
因島村上氏:早期から毛利方に協力。
来島村上氏:厳島の戦いを契機に毛利方に加担。
能島村上氏(村上武吉):独立性を保ちつつも、必要に応じて毛利方に協力。
後に一時的に毛利と敵対するも、再び臣従
5.織田信長との対決と村上水軍の活躍
毛利家が石山本願寺を支援した際、村上水軍は兵糧輸送を担い、第一次木津川口の戦いで織田水軍を撃破。
焙烙火矢(ほうろくひや)という独自兵器を用いて優位に立ちました
6.村上海賊の終焉
豊臣秀吉が天下統一を進める中で、1588年に「海賊停止令」を発令。
これにより村上海賊の活動は制限され、次第に解体されていきました。
来島村上氏は九州の内陸部に転封され、因島・能島の両氏は毛利氏の家臣団に組み込まれ、江戸時代には藩の船手組として活動を続けました
主な戦歴
背景:
毛利元就と陶晴賢の戦い。毛利方は劣勢でしたが、奇襲作戦を計画。
村上海賊の役割:
小早川隆景の仲介により、因島村上氏が毛利方に加勢。
夜間に兵を厳島へ上陸させ、海上封鎖を実施。
結果:
毛利軍が勝利し、中国地方の覇権を確立。村上水軍の名声も高まりました
背景:
織田信長が石山本願寺を攻撃。毛利氏は支援のために水軍を派遣。
村上海賊の役割:
能島村上氏を中心に、焙烙火矢(火薬玉)を用いた奇襲で織田方の九鬼水軍を撃破。
結果:
織田軍の大船団を焼き討ちし、毛利方が制海権を確保
背景:
織田信長が鉄甲船(鉄板で装甲した船)を投入し、再び本願寺を攻撃。
村上海賊の役割:
再び毛利方として参戦するも、鉄甲船の前に苦戦。
結果:
織田軍が勝利し、村上水軍の優位性に陰りが見え始める
背景:
豊臣秀吉による朝鮮出兵。
村上海賊の役割:
来島村上氏の来島通総(くるしまみちふさ)が水軍として参戦。
結果:
鳴梁海戦(めいりょうかいせん)で戦死。これを機に来島村上氏は衰退
戦術と兵器
船種:関船、小早などの小型船を用いて、機動力を活かした戦術。
兵器:焙烙火矢、鉄砲、弓、鎖鑓(くさりやり)、スマル(投げ鉤)など。
戦術:潮流を利用した奇襲、円陣・鶴翼・魚鱗などの陣形を駆使
村上海賊は、単なる「海賊」ではなく、戦国時代の海上戦術を極めた「海の武士団」でした。
特に能島村上氏の村上武吉(むらかみたけよし)は、戦術家としても知られています。
村上武吉
村上武吉(1533年~1604年)は、戦国時代の瀬戸内海を支配した能島村上氏の当主で、村上海賊の中心人物です。
幼少期に家督争いを経て当主となり、因島・来島の村上氏と連携し、三家を統率しました。
毛利氏と同盟を結び、第一次木津川口の戦いでは織田軍を撃破するなど、海戦で活躍。
関ヶ原の戦いでは西軍に属し敗北、戦後は毛利家の家臣団に組み込まれました。
海上交通の安全を守る「海の武将」として、戦略・外交に優れた人物でした。
厳島の戦い
厳島の戦い(いつくしまのたたかい)は、1555年(弘治元年)に現在の広島県・厳島で起きた戦国時代の重要な戦いです。
対戦勢力:毛利元就 vs 陶晴賢(すえはるたか)
場所:厳島(現在の広島県廿日市市)
結果:毛利元就の勝利
陶晴賢は主君・大内義隆を自害に追い込み、実権を握っていました。毛利元就の勢力拡大を警戒し、討伐に乗り出す。
毛利元就はその陶氏に対抗し、厳島に布陣した陶軍に対して奇襲作戦を決行します。
陶軍の上陸:陶晴賢は約3万の兵を率いて厳島に布陣。
毛利軍の奇襲:毛利元就はわずか数千の兵で夜間に海を渡り、厳島に上陸。
村上海賊の協力で船を使った奇襲が成功。
混乱と敗北:陶軍は撤退手段を失い、混乱。
陶晴賢は自害し、戦いは毛利方の圧勝。
この戦いに勝利したことで、毛利元就は中国地方の覇権を確立し、戦国大名としての地位を大きく高めました。
また、村上海賊の海上戦術が勝利に大きく貢献したことでも知られています。
村上海賊の役割
厳島の戦い(1555年)における村上海賊の役割は、毛利元就の奇襲作戦を成功に導いた「海の戦術家」として極めて重要でした。
毛利元就の海上作戦を支援
毛利軍は兵力で劣っていたため、海上からの奇襲が不可欠でした。
元就は小早川隆景を通じて村上海賊に協力を要請。
能島村上氏の村上武吉、来島村上氏の村上通康らが説得され、毛利方に加勢しました
奇襲の実行支援
村上海賊は闇夜と大潮を利用し、毛利軍を厳島へ密かに渡海させました。
豪雨の中、艪を漕ぐ音も雨音に紛れ、敵に気づかれずに上陸できたのは、村上海賊の海上技術と知識によるものです
陶軍の船を無力化
村上海賊は陶軍の軍船の艫綱(ともづな)を切断し、潮流に乗せて沖へ流すという戦術を実行。
これにより陶軍は撤退手段を失い、混乱に陥りました
戦局の逆転
村上海賊の加勢により、毛利軍は海上・陸上の両面で優位に立ち、陶晴賢を自害に追い込みました。
この勝利は毛利氏の中国地方制覇の足がかりとなり、村上海賊の名声も高まりました
村上海賊は、単なる海賊ではなく、戦国時代の「海の武士団」として、戦術・戦略の両面で毛利氏の勝利に貢献しました。
特に村上武吉の知略は、厳島の戦いの成功に不可欠だったとされています。
第一次木津川口の戦い
第一次木津川口の戦い(だいいちじ きづがわぐち の たたかい)は、1576年(天正4年)に大阪湾・木津川河口で行われた、毛利氏と織田氏の間の海戦です。
これは、織田信長と本願寺顕如(ほんがんじけんにょ)との間で続いた「石山合戦」の一環として行われました。
石山本願寺は織田信長に包囲され、兵糧が尽きかけていました。
本願寺は毛利輝元に救援を要請。
毛利氏は村上水軍、小早川水軍、宇喜多水軍、雑賀衆などと連合し、海からの補給を試みました
毛利方の戦力:約700〜800隻(村上元吉=父は村上武吉・村上景広らが指揮)
織田方の戦力:約200〜300隻(真鍋貞友・沼間伝内らが指揮)
戦術:村上水軍は「焙烙火矢(ほうろくびや)」という火薬を詰めた爆弾や火矢を用いて、織田方の船団を焼き払いました
結果:織田水軍は壊滅的打撃を受け、毛利方は石山本願寺への補給に成功
村上水軍は潮流を読み、夜間の奇襲や火攻めを得意とする戦術で、織田軍の大船を撃破。
特に能島村上氏の村上元吉が中心となり、戦術的勝利を導きました
織田信長にとっては、敵に包囲を突破された数少ない敗戦の一つ。
この敗北を受けて、信長は後に「鉄甲船(鉄板で装甲した船)」の建造を命じ、第二次木津川口の戦いに備えました。
この戦いは、村上水軍の戦術と海上戦力の高さを天下に示した一戦であり、戦国時代の海戦史における重要な転換点となりました。
関ヶ原の戦い
村上海賊の三家(能島・因島・来島)は、毛利輝元を総大将とする西軍に属していました。
能島村上氏と因島村上氏は、加藤嘉明が不在だった伊予国(現在の愛媛県)を攻撃するも、敗北し、能島村上の村上元吉は討死
来島村上氏は、来島通総の死後、通総の子・来島長親が家督を継ぎ、西軍に加担しましたが、戦後に改易され、豊後森藩(現在の大分県)に転封されました
能島村上氏の村上武吉は、関ヶ原本戦の裏で瀬戸内海沿岸の東軍勢力を攻撃する作戦を展開しました。
目的:瀬戸内海の制海権を握ることで、東軍の補給路を遮断し、四国・九州の東軍勢力を孤立させる。
行動:伊勢・知多半島の城を攻撃し、さらに伊予国の松前城に上陸。
降伏勧告を受け入れられたものの、夜間に奇襲を受けて敗退
関ヶ原の戦いで西軍が敗北したことで、村上海賊は大きな打撃を受けました。
来島村上氏:
豊後森藩に転封され、後に「久留島氏」と改姓。
海とのつながりはかろうじて保たれました
因島・能島村上氏:
毛利氏の家臣団に組み込まれ、江戸時代には萩藩の船手組として活動。
特に能島村上氏は約250年にわたり船手組の頭を務めました
村上海賊は、陸上の戦いとは異なる視点から戦局に影響を与えようとしました。
彼らの海上作戦は、補給路の遮断や沿岸支配を通じて、戦略的に重要な役割を果たしましたが、結果的には東軍の勝利によりその努力は報われませんでした。
投稿者から一言
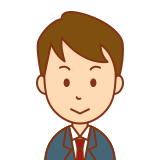
最後までご覧いただきありがとうございます。
水軍のイメージが強い村上海賊ですが、その海運技術を駆使し、瀬戸内海の治安を守っていたことも知っていただけたら幸いです。
これからも戦国時代をテーマに投稿を続けていくのでよろしくお願いします。
前回は「義」と「愛」の武将、直江兼続について履歴書風に紹介しました!
直江兼続の特技や自己PRを記載したので、面白おかしくい学べられるとおもいます
気になる方はぜひご覧ください<(_ _)>



コメント